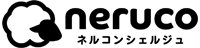引越しを機にベッドの購入を考えているけれど、今使っている布団をそのまま使い続けたいというときは、布団が使えるすのこベッドがおすすめです。すのこベッドは布団でもマットレスでも使えるだけでなく、通気性が高く、木の香りを楽しめるというメリットがあります。
ただし、すのこベッドのすべてで、布団もマットレスも使えるわけではありません。布団を使えるすのこベッドを購入するにあたっては、注意点もいくつかあります。
ここでは、すのこベッドのおすすめ10選を紹介するとともに、すのこベッドの特徴やメリット、選び方、使用の際の注意点を詳しくお伝えします。併せて、すのこベッドを快適に使うためのカビ対策も紹介しますので、すのこベッドの購入を検討している人はぜひ参考にしてください。
シンプルで頑丈なnerucoオリジナル天然木すのこベッド「バノン」
国産檜(ひのき)を使用した北欧風ステージベッド
室内で布団が干せる桐すのこマット
目次 [開く]
布団が使えるすのこベッドの特徴

一般的にベッドにはマットレスを乗せて使いますが、これは床板にかかる重みを分散するためでもあります。
厚みのあるマットレスを乗せれば一か所に重さが集中することがないため、ベッドの床板が破損するのを防げます。しかし、マットレスを乗せる想定で作られたベッドに敷き布団を直接敷いて寝ると、体重が1か所に集中してしまう可能性があり、最悪の場合はベッドの床板が割れることもあります。
布団が使えるすのこベッドはこうした点を考慮して作られており、敷き布団を直接敷いて寝たからといって壊れる心配はありません。マットレスを乗せても使える耐荷重で設計されているので、耐久性の面でも安心です。
また、布団が使えるすのこベッドのなかには、布団干しができるよう山折りにできるもの、M字型に立てられるものもあります。用途に合わせてさまざまな種類から選択できるのも、すのこベッドの特徴だといえるでしょう。
そのまま布団が敷けるおすすめすのこベッド10選

ベッドを買っても敷き布団を使い続けたいという人も、敷き布団が使えるすのこベッドを選べば問題ありません。ただし、取り扱いの注意点をきちんと把握しておき、対策についてもしっかり考えておくことが大切です。
ここでは、敷き布団でも使えるおすすめのすのこベッドをご紹介します。
| 商品名 | 特徴 |
|---|---|
| シンプルで頑丈なnerucoオリジナル天然木すのこベッド「バノン」 | 厚さ3cmの極太フレーム、極太の横桟 |
| 高さ4段階棚付きすのこベッド「バノンプラス」 | コンセント棚を備えたヘッドボード付き |
| 圧迫感なく設置できるロータイプすのこベッド | 天井との距離が取れるローデザイン |
| 国産檜を使用した北欧風ステージベッド | シンプルな北欧調デザイン |
| 総檜のヘッドレスすのこベッド | 檜のリラックス効果の高い香り |
| 大人も子供も使えるシンプルなヘッドレスすのこベッド | 圧迫感のないヘッドレスデザイン |
| タブレットスタンド付きのすのこベッド | 枕元で充電ができるコンセント付き |
| 棚付きのハイタイプすのこベッド | 床面下を大容量収納スペースとして使える |
| 室内で布団が干せる桐すのこマット | 桐を使用していて調湿効果・耐熱効果が高い |
| 三つ折り・二分割できる檜すのこマット | 使わないときにはコンパクトに収納できる |
シンプルで頑丈なnerucoオリジナル天然木すのこベッド「バノン」
頑丈設計で敷布団も使えるすのこベッド。
静止耐荷重350kg(JIS規格耐荷重7000N=約700kg試験合格品)をクリアしているので、大柄な人も安心です。
一般的なベッドにはない、厚さ3cmの極太フレームとすのこ床板を支える極太の横桟を採用しています。
高さ4段階棚付きすのこベッド「バノンプラス」
当社オリジナルの頑丈な天然木すのこベッドバノンにコンセント棚を備えたヘッドボード付きタイプのバノンプラスが登場!頑丈さはそのままに、枕元に便利な機能性が加わりました。耐荷重350kg(JIS規格耐荷重7000N=約700kg試験合格品)
圧迫感なく設置できるロータイプすのこベッド
天井との距離が取れるローデザインで、ゆとりのある空間を演出してくれるすのこベッドです。
一回り大きいフレームはボード部分を棚として使えるので、ベッド周りに時計やスマートフォンなどを置けるのもうれしいポイント。マットレスでも布団でもお使いいただける頑丈設計です。
サイトで見ていた見た目から変わらず、かわいいです!
国産檜(ひのき)を使用した北欧風ステージベッド
シンプルな北欧調デザインのすのこベッドは、和モダンなインテリアとも、北欧風インテリアとも相性が良く、温もりあふれる空間を演出してくれます。
頑丈なすのこ仕様のステージベッドなので、敷布団でも安定感があります。
総檜のヘッドレスすのこベッド
どの年代でも使えるシンプルなヘッドレスデザインのすのこベッド。
フレームにもすのこにも檜を使用しているので、リラックス効果の高い香りに癒されたい方にもおすすめです。静止耐荷重350kg(JIS規格耐荷重7000N=約700kg試験合格品)
新築の寝室にシングルサイズを2台置きましたがデザインもスッキリしていて購入してよかったです。
大人も子供も使えるシンプルなヘッドレスすのこベッド
森林浴をしているような清涼感あふれる香りで、癒し効果抜群の檜を使用したすのこベッド。
圧迫感のないヘッドレスデザインなので、狭いワンルームやスペースに余裕のない寝室にもおすすめです。静止耐荷重350kg(JIS規格耐荷重7000N=約700kg試験合格品)
タブレットスタンド付きのすのこベッド
枕元で携帯やスマートフォンの充電ができる、コンセント2口とタブレットスタンドが付いたすのこベッド。
棚付きのハイタイプすのこベッド
北欧産天然木を使用したカントリー調デザインが可愛らしいすのこベッドです。
床面下を大容量収納スペースとして使えるハイタイプで、ヘッドボードにはコンセント付き。
サイドガードがあるので安心して眠れます。
配達後、直ぐに説明書を確認し家内と組み立て、約1時間程度で終了。とても頑丈でデザインにも優れ、価格以上の価値あるもので、大満足でした。購入して良かったです。
室内で布団が干せる桐すのこマット
すのこ板1枚ずつにスリットが入っているので、通気性がさらにアップ。
天然の桐を使用しているので調湿効果、耐熱効果も高く一年を通して快適に眠れます。
三つ折り・二分割できる檜すのこマット
使わないときにはコンパクトに収納できる檜すのこマット。山折りにして布団を干すこともできるので、日中は留守がちな方も安心です。
檜の香りがお部屋をリラックス空間に変えてくれます。
すのこベッドのおすすめポイント

敷き布団が使えるすのこベッドには、以下のようにさまざまなメリットがあります。メリットの概要をそれぞれ見ていきましょう。
- 通気性が高く衛生的に使える
- 夏の蒸し暑さを軽減できる
- 木の香りを楽しめる
- 省スペース
- 布団とマットレス両方で使える
通気性が高く衛生的に使える
床に布団を敷いた場合は、毎日の布団の上げ下ろしが大変ですが、ベッドなら上げ下ろしの必要はありません。もちろん布団干しは必要ですが、すのこベッドは通気性が高いため、湿気を適度に放出してくれます。毎日布団を干さなくても、すぐにカビが生えたり、ジメジメしたりする心配はないでしょう。
すのこ部分を取り外しできるタイプなら、立てかけて湿気を放出することもできます。折りたたみ式のすのこベッドは、布団を干すのにも便利です。
また、床から約30cmの高さまでは、ホコリなどが舞い上がるハウスダストゾーンといわれています。すのこベッドを利用すれば、ハウスダストゾーンを避けて眠ることができるので、アレルギーがある人も安心です。
夏の蒸し暑さを軽減できる
すのこベッドは通気性・放湿性に優れているため、布団に熱がこもりにくいという特徴もあります。夏の蒸し暑い日でも、すのこベッドなら快適に眠れるでしょう。クーラーからの冷えた空気も適度にベッド下に入るため、さらに涼しく感じられます。
ただし、通気性の高さは冬の寒さにもつながります。冬は冷気が下からのぼってこないようにする対策が必要です。
木の香りを楽しめる
すのこベッドは木材で作られており、木のあたたかい素材感を楽しめます。木の香りには人をリラックスさせる効果があるとされており、木の質感はさまざまなインテリアとも合わせやすいという特徴もあります。すのこベッドは、木の香りが好きな人におすすめです。
また、木材には吸湿性や放湿性といった機能もあり、木材の種類によっては防臭、防ダニなどの効果を持つものもあります。木材の特徴をより活かしたい人は、木材の種類にもこだわってみましょう。
省スペース
すのこベッドのなかには、コンパクトに折りたためるものや、ロール式になっているものがあります。省スペースに収納できるのは、すのこベッドならではの特徴だといえるでしょう。
ベッドを置く広いスペースがない人や、来客用として一時的にベッドを増やしたい人に、すのこベッドはおすすめです。折りたたみ式やロール式のものは重量も軽いため、ひとりでも簡単に取り扱えるでしょう。
布団とマットレス両方で使える
本記事でも紹介しているように、すのこベッドは布団とマットレスの両方で使えます。そのため、布団からベッドに変える場合でも、ベッド購入に併せてマットレスを購入する必要はありません。布団が好きな人もベッドのメリットを活かせるのです。
生活スタイルが変わっても、同じベッドを使い続けられるのも魅力の一つ。製品によってはさまざまなサイズの布団やマットレスに合わせられます。
布団が敷けるすのこベッドのメリット・デメリット
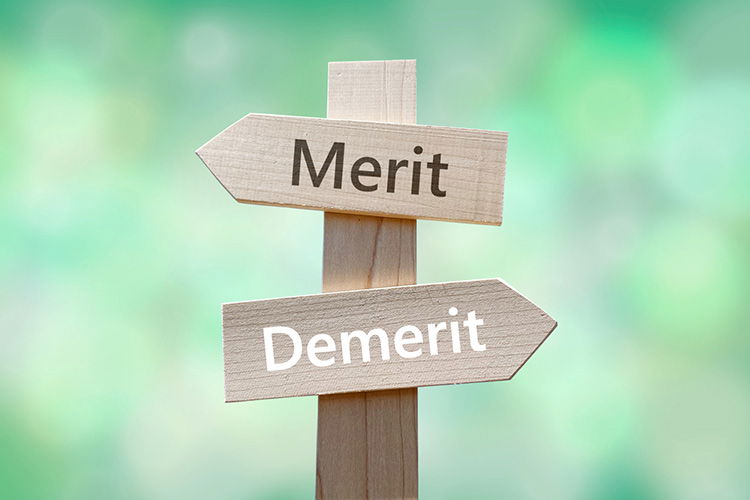
すのこベッドに布団を敷くメリット・デメリットを解説します。メリットとデメリットの両方を知り、デメリットを小さくできるよう対策しましょう。
すのこベッドに布団を敷くメリット
すのこベッドを利用すると、布団を上げ下ろしする必要がなくなります。布団を干す場合も、床から布団を持ち上げるのに比べて、ベッドから布団を持ち上げる方が楽に持ち上げられます。定期的に布団を干せば床板の湿気も放出されるため、すのこのメンテナンスも効率的に行なえるでしょう。
また、折りたたみ式のベッドなら、ベッドがそのまま布団を干す台にもなります。ベランダがなく布団を干せない人や、日照時間が短い冬場でも布団をしっかり干したい人にも、すのこベッドはおすすめです。
さらに、布団をベッドに敷くことで、寝る高さを上げられるのもメリットです。適度な高さがあることで立ち上がりが楽にできますし、ちょっと腰かけたいときにも便利でしょう。
すのこベッドに布団を敷くデメリット
すのこベッドは硬いため、直接布団を敷くとすのこの硬さが伝わりやすくなります。すのこベッドに布団を敷くなら、ある程度厚みのある布団が向いているでしょう。
また、すのこベッドに布団を敷くと、マットレスを使用する場合と比べて、寝る位置が床面に近くなってしまいます。そのため、床からの冷気やハウスダストの影響を受けやすくなる点には注意が必要です。
冷気は暖房器具や暖かい寝具の使用などで対応し、ハウスダストにはこまめな掃除や換気などで対応しましょう。
布団が敷けるすのこベッドの選び方

すのこベッドを選ぶ際は、素材や機能性、高さ、耐久性、価格を比較して、自分に合うものを選びましょう。
素材を比較して選ぶ
すのこベッドに使われる素材は木材が一般的です。代表的な種類には、杉、桐、檜、パインなどが挙げられます。
それぞれ以下のような特徴があり、メリット・デメリットも異なります。
| 素材 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 杉 | ・軽量で柔らかい ・比較的安価 |
・軽量 ・香りが良く防虫効果がある |
・傷つきやすく耐久性が低め ・湿気を吸いやすい |
| 桐(きり) | ・非常に軽量でやわらかい ・湿気に強い |
・軽量 ・防湿効果が高い ・耐火性が高い |
・傷つきやすく強度が低め ・高価 |
| 檜(ひのき) | ・高級木材 ・耐久性がある |
・耐久性が高い ・防虫効果 ・腐りにくい ・香りが良くリラックス効果がある |
・高価 ・重い |
| パイン | ・針葉樹で柔らかい ・比較的安価 |
・加工がしやすくデザインが多様 ・明るい色合いのため部屋に馴染みやすい |
・やわらかく傷つきやすい ・湿気に弱い |
機能性を比較して選ぶ
自分に必要な機能が備わっているかどうかを基準にベッドを選ぶのも一つの方法です。ベッドのある生活をイメージしながら、どのような機能が必要か考えてみましょう。
おもなベッドの機能には、収納付き、コンセント付き、照明付き、高さ調節機能付き、サイドテーブル付き、折りたたみ式、ヘッドレスタイプ、パネルタイプなどがあります。
それぞれの特徴やメリット、向いている人についても以下でまとめていますので、自分に合うものがないかチェックしてみてください。
| 機能・種類 | 特徴 | メリット | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 収納付き | 引き出しタイプ、跳ね上げタイプ、チェストタイプがある | ・本や小物を収納でき、スペースの有効活用ができる ・跳ね上げタイプはベッド下がすべて収納スペースなのでラグなどの長物や羽毛布団なども収納可能 |
・部屋の収納が少ない人 ・収納スペースを増やしたい人 |
| コンセント付き | コンセントのほか、USBポート付きもある | ・スマートフォンや電子機器を充電でき | ・ベッドでスマートフォンやタブレットを充電したい人 |
| 照明付き | ヘッドボードに照明が内蔵されている | ・読書や作業に便利 ・部屋の雰囲気作りにも役立つ |
・ベッドで読書や作業をする人 ・ベッド周りをおしゃれにしたい人 ・夜中にトイレに行くことが多い人 |
| 高さ調節機能付き | ベッドの床面高さを調節できる | ・自分の好みに合わせていつでも高さを調節可能 ・ローベッドや、ベッド下収納が作れるハイベッドにもなる |
・模様替えや、ライフスタイルに合わせてベッドスタイルを変えたい人 |
| サイドテーブル付き | サイドテーブルが一体化されている | ・飲み物や眼鏡、時計などの小物を置くスペースが確保できる | ・ベッド周りに必要な物を置きたい人 |
| 折りたたみ式 | コンパクトに折りたたみ可能、ロール式もある | ・使用しないときにコンパクトに収納可能 ・スペースを節約可能 ・移動に便利なキャスター付きのものもある |
・部屋のスペースを有効活用したい人 ・部屋が狭い人 ・来客用ベッドがほしい人 |
| ヘッドレスタイプ | ヘッドボードがない | ・シンプルでミニマルなデザイン ・部屋のスペースを広く使える ・棚がないのでホコリが気にならない |
・部屋を広く使いたい人 ・シンプルなデザインが好きな人 |
| パネルタイプ | 棚がないフラットなパネル型ベッド | ・シンプルでミニマルなデザイン ・背もたれとして使える ・圧迫感がない |
・部屋を広く使いたい人 ・シンプルなデザインが好きな人 |
高さを比較して選ぶ
ベッドの高さは、使い勝手や必要な機能、部屋の雰囲気などに影響するため、自分の好みに合わせて選択しましょう。
低め、中程度、高め、ハイタイプの4つに分けられ、それぞれにメリット・デメリットがあります。
| 高さ | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 低め | ・床面とほぼ同じ〜10cm程度の高さ ・「ローベッド」や「ステージベッド」などと呼ばれる |
・天井を広く感じ、開放感がある ・落下時の危険性が少ない |
・ベッド下のスペースを収納として活用できない |
| 中程度 | ・一般的な高さで、床面までの高さが30〜40cm程度のものが多い | ・購入の選択肢が幅広い ・腰かけるのに便利 |
・ベッド下のスペースを収納として使えるが、高さが物足りないと感じるかも |
| 高め | ・床面下に収納スペースが付いたものが多い ・床面が50cm以上になることが多い |
・機能性に優れる ・ベッド下を有効活用できる ・立ち上がりが楽 |
・価格が高い ・重心が高く、サイズが大きい |
| ハイタイプ | ・高さが200cm近いものもあり、ロフトベッドやシステムベッドに分類される | ・ベッド下を大きく活用できる ・ベッド下にもマットレスや布団を敷くと2段ベッドのように使える |
・天井が近く、大人は圧迫感を感じることがある ・移動や組み立てで労力が必要 |
サイズを比較して選ぶ
ベッドのサイズ選びも重要なポイントの一つです。使用人数や部屋の大きさ、搬入経路を確保できるかをふまえてサイズを検討しましょう。
おもなベッドサイズは以下のとおりです。
| サイズ | 寸法 | 対応人数 |
|---|---|---|
| セミシングル | 幅80~90cm×長さ195~200cm | 1人用(子供、小柄な方) |
| シングル | 幅97~100cm×長さ195~200cm | 1人用 |
| セミダブル | 幅120cm×長さ195~200cm | 1人用(ゆったり寝たい方や体格が大きい方) |
| ダブル | 幅140cm×長さ195~200cm | 1~2人用(ゆったり寝たい方、夫婦・カップル) |
| クイーン | 幅160cm×長さ195~200cm | 2人用(夫婦・カップル) |
| キング | 幅180~200cm×長さ195~200cm | 2~3人用(大人+小さなお子様) |
| ショート | 長さ180cm | 1人用(160cm以下の方) |
| ロングサイズ | 長さ205~215cm | 1人用(180cm以上の方) |
耐久性(耐荷重)を比較して選ぶ
耐荷重とは、「その商品が耐えられる最大の荷重」を指します。ベッドの場合、「何kgまでの重みに耐えられるか」を表した数値が「耐荷重」です。すのこベッドの耐久性はこの耐荷重の数値で表され、数値が高いほど耐久性が優れた製品といえます
耐荷重を考える際は、利用する人の体重に加え、寝具やマットレスなど、ベッドの上に載せるものすべての重みを考慮する必要があります。また、耐荷重は静止した状態での重さを基準としているため、ベッドの上で飛び跳ねたりすると、耐荷重内であっても破損のリスクがある点に注意しましょう。
価格を比較して選ぶ
すのこベッドの価格帯は1万円から3万円未満が一般的です。価格が高いほど品質は良くなりますが、重量が増して移動や組み立てが難しくなるというデメリットもあります。価格だけで選択せず、素材や機能性などのその他の要素もふまえて選びましょう。
価格帯ごとのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 価格帯 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 安いベッド (~2万円以下) |
・価格が手頃なものが多い ・組み立てが比較的簡単 ・軽量で移動が楽 |
・耐久性が低い(短期間の使用に向いている) ・素材が安価なため、見た目が劣る ・機能が少ない ・保証期間が短い、またはない |
| 高いベッド (2万円以上) |
・高品質な素材で耐久性が高い(天然木、国産など) ・洗練されたデザイン ・機能が豊富(収納、コンセント、照明、高さ調節など) ・保証期間が長い |
・価格が高い ・重量があり、移動や組み立てが大変 |
布団が敷けるすのこベッドの注意点

敷き布団が使えるすのこベッドには、マットレスにはない便利なポイントや床に布団を敷く場合にはないメリットがありますが、良い点ばかりではありません。
使う際に気を付けた方が良い点、寝具の見直しが必要な部分もあるので、購入の際には注意点に対してどう対策を取るかも考えておきましょう。
すのこベッドで注意したい点は以下の3つです。それぞれ内容を見ていきましょう。
- 冬は寒く感じる場合がある
- きしみ音が発生する可能性がある
- 薄い布団だと底付き感が出やすい
冬は寒く感じる場合がある
すのこベッドを設置する場所にもよりますが、冬は寒さを感じることもあります。
暖房が効いた部屋でも暖かい空気は上の方にたまり、冷たい空気は下にたまります。すのこベッドは床板がすのこ仕様なので、その冷たい空気がベッド下から入り込み、布団が冷えてしまうため、寒いと感じてしまうのです。
冬の寒さに備えるために、暖かい空気と冷たい空気の層が2つに分かれてしまわないよう工夫しましょう。暖房を使用するときにはサーキュレーターで空気を循環させる、ベッドの下にラグなどを敷いて床からの冷えが伝わらないようにするなどで、寒さを和らげられます。
きしみ音が発生する可能性がある
すのこベッドは縦と横に板を組み合わせているため、使用していると板同士が擦れあってきしむこともあります。フレームと床板の間に隙間ができてきしみ音が発生する、床とフレームの摩擦できしむなど、さまざまなパターンできしみ音が発生する可能性があります。
ベッドからきしみ音がしたら、どこから音がしているのか、まずは音の発生源を突き止めましょう。原因がわかったら、原因に合わせて適切に対処します。隙間ができてきしみ音がするときは緩衝材になる布などを挟む、床との摩擦ならカーペットやラグを敷くなどするとよいでしょう。
薄い布団だと底付き感が出やすい
敷き布団を直接すのこベッドに敷くと、マットレスを使う場合よりも底付き感が出やすくなります。
固めの寝心地が好きな人であれば特に問題なく寝られるかもしれませんが、起きたときに体が痛いと感じる場合は、厚みのある敷き布団に変えるか、敷き布団に厚手の敷きパットを敷く、布団の下にマットレスを敷くなどの対策が必要です。
すのこベッドを快適に使うにはカビ対策が重要!

すのこベッドは通気性に優れ、カビが発生しにくいという特徴があります。しかし、布団を敷いたまま放置していると湿気がたまり、カビが発生する可能性が高まります。
カビの発生を抑えるためには、以下の5つの点に注意しましょう。
- 対策①布団・ベッドをこまめに干す
- 対策②すのこベッドの配置場所を変える
- 対策③部屋を換気する
- 対策④除湿器やエアコンの除湿機能を活用する
- 対策⑤除湿シートを利用する
また、ベッドフレームにカビが生えてしまったときの対処法は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
対策①布団・ベッドをこまめに干す
最も効果的な湿気対策が、布団とベッドをこまめに干すことです。布団とベッドを干すことで、布団とすのこが吸い込んだ湿気を放出させ、カビが発生するのを防ぎます。
布団は毎日たたむのが理想的です。すのこが取り外せる場合は、壁に立てかけるなどして湿気をとります。筋力に自信がない人は軽めのベッドを選んでおくと、干す労力が減るでしょう。
梅雨の時期や夏場は湿気がたまりやすいため、さらに注意が必要です。シーツ類も定期的に洗い、湿気や汚れがたまらないようにしましょう。
対策②すのこベッドの配置場所を変える
窓の近くにベッドを置いていると、結露によってベッドが濡れ、カビの原因になってしまいます。また、ベッドと壁の間の通気性が悪くなり、カビが発生しやすくなります。ベッドは風通しの良い場所に設置するのが基本です。窓際や壁際にぴったりとつけるのは避け、ある程度空間に余裕を持たせましょう。
また、すのこベッドのなかには、ベッド下部に収納スペースが付いているものもありますが、ベッド下に物を置きすぎると、すのこの通気性が落ちてしまいます。すのこのメリットである通気性を損なわないためにも、物を収納し過ぎないようにしましょう。
対策③部屋を換気する
布団やベッドを干していても、部屋に湿気がたまっていたら、すぐに布団とベッドが湿気を吸収してしまいます。湿気が部屋にたまらないよう、こまめに部屋を換気しておきましょう。
部屋の対角線にある窓や入口を解放すると、効率良く空気を循環させられます。サーキュレーターや扇風機も併用すると効果がアップするので、お持ちの方はぜひ活用してみてください。
なお、夏の暑い時期や冬の寒い時期など、クーラーや暖房器具を使用している場合でも、定期的な部屋の換気は必須です。寝室を心地良い空間にするためにも、忘れずに換気を行ないましょう。
対策④除湿器やエアコンの除湿機能を活用する
外で布団を干す場所がないときや、雨で湿度を逃がせないときは、除湿器やエアコンの除湿機能を活用しましょう。湿度が60%を超えるとカビやダニが発生しやすくなり、湿度が40%を下回ると喉や肌が乾燥しやすくなります。
湿度計で湿度をチェックしながら、湿度50%前後を目安に湿度を調節しましょう。サーキュレーターや扇風機と組み合わせると、より除湿効果がアップします。
対策⑤除湿シートを利用する
湿気対策として、布団とベッドの間に除湿シートを敷くのもおすすめです。除湿シートは乾かせば繰り返し使えるものも多く経済的です。毎日布団をたたむのが難しい人や、ベッドを頻繁に干せない人は、まずは除湿シートを採り入れるところから始めてみましょう。
布団が敷けるすのこベッドを選ぶなら「ネルコンシェルジュ」!
一般的に、ベッドを買うならマットレスも必要といわれていますが、すのこベッドならマットレスを使わずに敷き布団を使えるものもあります。
今ある布団を使いたい、マットレスはメンテナンスが面倒という人には、敷き布団が使えるすのこベッドがおすすめです。素材や機能性、高さ、サイズ、耐久性(耐荷重)、価格をふまえて自分に合ったものを選択しましょう。
また、通気性に優れるすのこベッドでも、手入れを怠るとカビが発生してしまう可能性があります。定期的に布団を干したり、除湿器や除湿シートを使用したりするなどして、ベッドの湿気を逃がせるよう対策しましょう。
ベッド・マットレスの通販専門店「ネルコンシェルジュ」では、ここで紹介したもの以外にも、布団が使えるすのこベッドを数多く取りそろえています。実店舗を持たない販売スタイルや工場直送の流通ルートなどを活かし、品質の良い商品を低価格でご提供いたします。
すのこベッドをほかにも見比べたい方は、ぜひこちらのページもご覧ください。